これまでの成果とこのサイトについて
情報の透明化を目指して
製薬会社の売り上げの約9割は、医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」です。その売り上げを増やすために、製薬企業は様々なプロモーション活動を行い、医療者に寄付金や謝金の形で金銭を支払っています。
製薬企業はそのデータを公開していますが、それらのデータを統合したデータベースは、日本には存在しませんでした。そのため、特定の医師が受け取った金銭の総額を明らかにしたり、製薬会社間で比べたりすることができませんでした。
以上を踏まえ、我々は独自に製薬マネーデータベース「Yen For Docs」を作成し、公開を行うこととしました。最初にデータベースを公開したのは、2019年1月です。
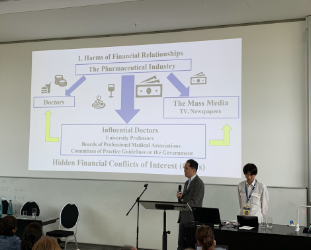
また、我々がまとめた論文によると、公開が開始された2019年1月15日から2021年5月24日にかけて、35万4863人からのべ60万4903回のアクセスがあり、総ページ表示(PV)は563万5087回でした。ある情報筋によると、一般的な企業のコーポレートサイトでは、1ヶ月あたりのPVの目安は3000~1万程度とされています。Yen For Docsは1ヶ月平均20万PV以上を獲得している計算ですから、いかに多くの方々が訪問してくれているかが分かります。
製薬マネーデータベースは、医療現場の透明化を大きく前進させてきました。このような公開の趣旨と目的を踏まえ、Yen For Docsが適切に利用されることを希望しています。
医学論文
- 日本医学会・同連合から「診療ガイドライン策定にかかる企業等との関係透明化に関する要請」が、日本医学会連合加盟学会に行われる。(2019年10月30日)
この要請には、以下3つの論文が引用された。
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2733427
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2731682
https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(19)30417-3/fulltext -
国内の製薬マネーに関連する研究不正としては「ディオバン事件」が最も有名な例だ。このディオバン事件に関わる臨床研究の論文著者の多くがディオバン事件発覚から3年を経てからも製薬企業から原稿執筆料、講演料、コンサルタント費等を受け取っていることが明らかになった。(2019年5月17日)
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2733427 - 当HPを利用して外部チームが論文作成、発表を行い、製薬マネーデータベース活用の範囲が広がっている。
シンポジウムなど
- 世界探査報道ジャーナリズムネットワーク(GIJN)アジア大会in韓国(2018年10月)
- GIJN世界大会inドイツ(2019年9月)
- オンランシンポ「医師は製薬会社の歯車か」(2020年8月8日)
https://youtu.be/R7UDDFs3zsM - 「現場からの医療改革推進協議会」第15回シンポジウム(2020年11月7日)
- 製薬マネーデータベース一般公開シンポジウム開催(https://youtu.be/Atfn0javJz4)
TANSAとの共同研究(2016~2018年)
2019年、文部科学省は、この製薬マネーデータベースを調査に使用しました。その結果、2016年度に2,000万円以上を得た大学教授は7人いたことを発表し、国会で大学に対して医学部医師の兼業規定や倫理規定の見直しを求める考えを表明したのです。
このデータベースを活用した報道や研究で上げてきた成果をお伝えします。
報道
- 2016年度に製薬会社からの謝金などを年間1,000万円超受け取っている医師が110人おり、 総額は266億円に上っている(2018年6月8日)
- 2017年度製薬マネーベースで、医師個人に273億円、学会・大学研究室などに357億円の資金提供が行われていることがわかった(2019年5月26日)
- 文部科学省が大学の勤務医を対象にした調査で、製薬会社から1,500万円超の報酬を得た医師が29人いた。そのうち10人が糖尿病の専門医、8人が循環器内科医だった。(2019年11月7日)
- 香川大教授、認知症薬の製薬6社から年間1900万円超の副収入。論文では第一三共の認知症薬を「ごまかし」て評価していた(2020年10月30日)
データベースの使用に当たってのお願い
データベースは、製薬各社がホームページ上で公表している医療関係者への支払い情報に基づいて作成しています。正しく表示されるよう精査していますが、氏名、組織名、金額の誤記または脱落がある可能性もあります。
誤りにお気づきになりましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
製薬会社が公表した情報に誤りがある場合は、当該製薬会社にご相談ください。
メディアまたは研究者の方が当データベースを利用し記事や論文を公開される場合には、出典として、必ずデータベース名と作成者(2016年度〜2019年度データは医療ガバナンス研究所と Tansaの共同研究による、2020年度以降は医療ガバナンス研究所による)のクレジットの記載をお願いいたします。
同姓同名の方もおり、可能な限り判別してアルファベットで表記しました。判別できなかった場合は「判別不能」としています。
年度ごとに集計しているため、2016年度と2017年度に「例:山田太郎a」という方がいた場合、同一人物とは限りません。
また、氏名の漢字は新字体で表記していますが、一部に表記の揺れなどがあります。旧字体がある場合は旧字体でも検索ください。
用語の説明
- 透明性ガイドライン
- 医師が製薬会社から受けた金銭情報を公開する欧米での動きを受け、大手製薬会社が加盟する業界団体の日本製薬工業協会が2011年に策定。加盟製薬会社はガイドラインに従い、医師個人や医療機関、研究機関への支払い情報を公開している。
- A項目(研究開発費等)
- 臨床研究や治験、製造販売後臨床試験などの研究開発に対する資金提供。
- B項目(学術研究助成費)
- 学術研究の支援を目的に、主に大学や研究機関に対して支払われる。学会などの共催費用も含まれる。
- C項目(原稿執筆料等)
- 主に医師個人に対して支払われる謝礼。セミナーなどの講演料や原稿執筆料、コンサルティングに対する業務委託の費用が含まれる。
- キーオピニオンリーダー(KOL)
- 医療業界で影響力を持つ医師。大学病院の教授や、大病院の院長クラス、ある領域の権威など。製薬会社は自社製品の販売促進のために、KOLに働きかけ、KOLからの発信によって他のドクターにも最新の製薬情報の普及・浸透をはかる。インフルエンサーと呼ばれることもある。
- 診療ガイドライン
- 病気の予防・診断・治療・予後予測など、診療の根拠や手順について最新の情報をまとめた指針。使用が推奨される薬も明記されており、医師はガイドラインを見て治療方針や処方する薬を決めていくことが多い。各診療科の学会などが委員会を形成し、ガイドラインを作成する。
- PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
- 厚労省が所管。薬機法に基づき医薬品・医療機器などの品質、有効性、安全性を審査する。新薬などはPMDAの審査を通過したものを厚生労働大臣が承認することで、国内で使用できるようになる。
- 薬価算定組織
- 新薬が正式に承認されたあと、厚労省が提出した原案をもとに薬の値段を決める医師や研究者で構成された組織。委員は厚労省が選出する。
- 専門医
- 各学会が認定した資格を持つ医師のこと。通常、試験や経験年数、研修、学会・研究発表等の要件を満たした場合に認定される。
